
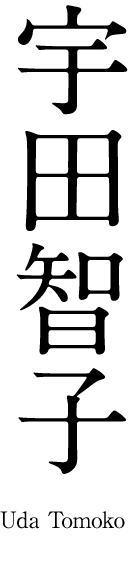

【略歴】
1980年、神奈川県生まれ。2002年にジュンク堂書店に入社し、池袋本店で人文書を担当する。2009年、那覇店開店に伴い沖縄に異動。2011年7月に退職し、同年11月11日、那覇市の第一牧志公設市場の向かいに「市場の古本屋ウララ」を開店する。 著書に『那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた<ウララ>の日々』(2013年7月・ボーダーインク刊)がある。 2014年3月、第7回「(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞」を受賞。
【授賞理由】
気がついたら公設市場の向かいで三坪ばかりの古本屋の店主になっていた、と語る著者は、その体験を身辺雑記ふうな語りで活写してみせる。しかしそこには、自分にとって生きている、暮らしているとはどういうことか、自分と他者、その間をつなぐ本の存在とは何であるのか、それらを見つめ、言葉にしてゆこうとする著者の姿が表わされていた。自分の息づかいと同じリズムで考え、ことさら無理をせず、あえて修辞を抑えた文章に、身ひとつで世界全体を見晴るかし、対峙してゆこうとする表現者としての氏の覚悟と可能性をわれわれは見た。今後の活躍を期して当賞を贈りたい。
【本との話(2014-04-04)】
1月の終わりの昼さがり、店で本を何冊か買ってくれた男性に話しかけられた。
「あなたの本を読みました」
去年の7月に出版した『那覇の市場で古本屋』のことだ。
「面白かったです。これからも書いていくのですか」
「そのつもりです」
「どんなものを」
「まだわかりません」
「あなたにとって、〈書く〉とはいったい何ですか」
思わず相手の顔を見返した。
「どうしてそんなことを聞くのですか」
すると相手はふっと笑って、机に名刺を置いた。〈特定非営利活動法人 わたくし、つまりNobody 理事長〉とある。
「私はこういう名前の賞を主催しています。あなたが最終候補者に選ばれました。受けてくださいますか」
店頭に座っていると思いがけないことは日々起こる。そのなかでも極めつきの変な出会いだった。
池田晶子さんという文筆家がいた。大学に属さず平易な言葉で哲学エッセイを書いていた。『14歳からの哲学』(トランスビュー)は刊行10年で28刷のロングセラーになっている。
池田さんが2007年に46歳で亡くなったあと、彼女のようにひたすら考えて言葉で表す人を顕彰するため、〈(池田晶子記念)わたくし、つまりNobody賞〉が設立された。
賞の資料を読みながら、これは新手の振り込め詐欺ではないかと不安になった。人の虚栄心につけこんで、お金を奪ったり恥をかかせたりするのでは。
こんなふうに考えてしまったのは、相手を信用していないというより自分に自信がないせいだ。池田さんの本は前から読んでいて、賞の存在も知っていた。だからこそ自分がそれに値するとは思えなかった。
それでも、この賞はすでにある作品を評価するのではなく、その人の可能性を応援するための賞だと知って心が動いた。引き受けることで私にも責任感が生まれて、より堂々と仕事に打ちこめるかもしれない。
こうして受賞を決めて新聞にも記事が出て、たくさんの人が声をかけてくれた。
「おめでとう。で、何の賞なの」
これが難しい。名称すらなかなか覚えられなかった。〈わたくし、つまりNobody〉は池田さんの初期のエッセイのタイトルでもある。〈私を考え、私を突き抜け、普遍に至る〉〈もはや「私」はNobody、そして、Everywhere〉
わかるようなわからないような。でもこれが私の目指す境地だというのはわかった。
市場の店先に座って、そこで見えたものばかり書いている。ごく個人的な記録でも、突きつめれば場所も時代も超えた何かに通じることもあるはずだ。そんな夢物語を一緒に信じてくれる人たちが現れたのだから、このまま続けていくしかない。
ガーブ川を蹴りあげて市場通りのアーケードを突き破るように、新しい景色が見たい。
【ブックリスト】

那覇の市場で古本屋 ひょっこり始めた<ウララ>の日々
大学を出て大手書店の人文書担当として活躍していた彼女は、次第に地方出版社の本と活動に関心を寄せていく。数年後、気がついたら、那覇の市場の向かいで小さな古本屋の店主になっていた。自分と他者、その間をつなぐ本の存在、そこから見えてきたものとは──。
ボーダーインク◆定価1,600円(本体価格)
2013年7月刊